071110「見」:鹿乗川から学ぶ~井町さんを招いての授業~
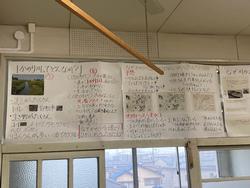
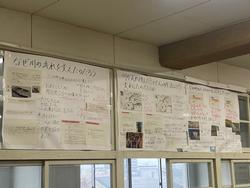
本日、4年3組の社会「鹿乗川の先人 大発見!」は、市議会議員の井町さんを招いての授業でした。教室には「鹿乗川ってどんな川」「なぜ川の流れを変えたのだろう」「川の流れを変えたことで人々の生活はどう変わったのだろうか」「今の町の人の鹿乗川に対する思いは?」といった学習の足跡が残されています。そうしたことを踏まえて、今日は井町さんに質問をしたり、説明をしてもらったり…、直接、わたしたちの鹿乗川について教えてもらいました。
今日の授業での学びから、3組の子たちはどんな発見をしたのでしょうか。すてきな学びをしていますね。
今日の昼の休み時間に、元気な矢南っ子を見ることができました。昼放課が始まると同時に、「ドッジボールするぞ!」「鬼ごっこやる人、朝礼台に集合!」「〇〇先生呼んでくるね。みんなで遊ぼう!」といった楽しそうな声が聞こえてきます。また、長放課にちょっともめていた子たちが、昼放課には仲よく遊んでいる様子が…!?仲直りしたのかな?
「ごめんなさい」「いいよ」で終わるもめごともあれば、しばらく心のどこかにしこりが残るもめごともあります。学校の中では、いろいろなもめごとが起きるものです。
先日、あるクラスで「泥のついたサツマイモをきれいにする方法」を尋ねてみました。出てきた答えは、「水につけて洗う」「たわしでこする」など。そこで、あるドラマで紹介されていた言葉を伝えました。
◆「泥のついたサツマイモ。どれ一つとして同じイモはありません。そして、おけの中でイモ同士がぶつかり合うことで、泥が落ちていく。だから、きれいになるのです。水だけではきれいになりません。きれいになるのは、自分の力(イモ同士がぶつかる力)であり、仲間の力(水やたわし)でもあるのです。」
もめごとを解決するには、水やたわしのような第三者(先生など)の力だけではうまくいきません。サツマイモの泥が落ちるように、友達同士がぶつかり合うことで、もめごとの解決の糸口が見つかるのかもしれません。
放課の過ごし方には、勉強以上に大切なことがあるように感じます(もちろん、勉強も大事ですよ)。子どもたちを見守りながら、時には「水」のような存在でありたいと思っています。
運動場で駆け回る矢南っ子、教室で談笑する矢南っ子、一人でじっくり本と向き合う矢南っ子…。それぞれの過ごし方の中に、「学び」があるようです。





