070822「WBGT測定器を片手に…」:二十四節気の14番目「処暑」


今週から部活動を再開しています。顧問の先生は、子どもたちの顔や動きをこまめに見ながら声をかけ、指示を出すときは日陰で短く、またWBGT測定器で値を確認して…。久しぶりに体を動かした子もいると思います。体調がおかしいなと感じたら、すぐに近くの人に伝えてください。登下校も心配ですので、複数で帰る、途中で水分補給をするなど、自分の体に目を向けてください。
矢南っ子のみなさん、今後は部活動だけでなく、学校生活の中でも、自分の体調の異変にはSOSを出してくださいね。
◆明日は暦の上では「処暑」。「暑さが止む」という意味から「処暑」といわれています。「処」という漢字は音読みで「しょ」、訓読みで「ところ」などの読み方があり、「その場にとどまる」や「一つの場所に落ち着く」などの意味があります。なので、この時期から次第に暑さがおさまってくるとされています。
昨日は名古屋で39℃の今年の最高気温を記録、昨日までで体温超えの37℃以上が6日連続、猛暑日にいたっては34日です。しかし、何もかも同じ日はなく、少しずつ少しずつ変化しています。二十四節気などの言葉を通して、朝、夕方の空気感、季節のちょっとした変化を、こういった言葉で実感することができると思います。暑さの中の季節の移ろいにも目を向けられたらなと思います。
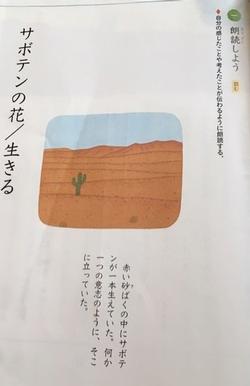
◆おととしまでの6年生の国語の教科書には、「サボテンの花」というやなせたかしさんの文章が載っていました。1学期、この文章をあるクラスで紹介したとき、ある子が「『ぼくが死んでも、一つの命が生きるのだ。生きるということ は助け合うことだと思うよ。』生きるためには自分だけで生きられないと思いました。周りの人を大事にしていきたいです。」、またある子が「最後に、だれも見る人もいないのに美しい花を咲かせたサボテン。自分を大事にする気持ちがあるから美しい花になったと思います」…と、話してくれました。『読む』ことを自らの経験や考えと関係づけて思いをもつことができています。国語の授業の『文章を読む』という大切な力をもっていると私は思いました。
2学期の学習は、どの教科もその学年で学ぶ核となる、今のみんなに必要な内容となっています。1学期にクラスの仲間と学び合う楽しさを味わってきました。そんな矢南っ子と、2学期も授業を通して、いろいろな力を身に付けられるように、いっしょに楽しい時間をつくっていきましょう。
◆ちなみに、やなせたかしさんと言えば、アンパンマン!アンパンマンは、敵(てき)をゆるす心をもっています。いじわるをしてくるバイキンマンと、仲良くかたを組む場面もあります。学校生活は、いつも楽しいときばかりではありません。周りの人とけんかをしたり、もめたりすることもあります。そんなとき、アンパンマンを思い出してほしいな。けんかをのりこえた先の「仲の良さ」。学校は、人とのかかわりを通して成長するのだと思います。
夏休み明け、みんなと過ごせる日を楽しみにしています。




